今日の車の中で聞こえてきたのは、この音源、マヌエル・マリア・ポンセの「スペインのフォリア」による変奏曲とフーガです
20代前半にレコードを買って、楽譜も出版されていたので練習しました
変奏曲なので、それぞれ断片的に弾いていました
難易度高いんで、もちろんちゃんとは弾けませんでした
どの変奏もすごく味わい深いです
ちなみにジョン様がこのレコードを録音したのは1978年4月です
ジョン様37歳ですね、ちなみに自分は17歳です
演奏はもちろんなんですが、このレコードの録音がすごく好きです
環境のリバーブが少ないんですね
ギターの響きしか録音していません
みたいなジョン様の録音、大好きなんですよ
このレコード以外でパッと思い浮かぶのはバリオス(こちらの音源)とか、ボッケリーニとかのですかね
もちろんそれ以外の録音も全部好きですよ!!


録音されている曲はこちら
- 「スペインのフォリア」による変奏曲とフーガ
- 前奏曲/バレット
- 3つのメキシコ民謡
a) 小鳥うりの娘
b) わが心よ、君ゆえに
c) ラ・ヴァレンティーナ - ワルツ
- しおれた心/8ヶ月前/愛する母
■録音データ
SIDE A 24’15”
SIDE B 6’25″/ 5’08 / 2’50 / 7’27”
1978年4月 ロンドン、AIRレコーディング・スタジオ
プロデューサー:ロイ・エマーソン
エンジニア:マイケル・スターブロー
濱田滋郎さんによる解説がジャケット裏面にありました
いつもながら、ためになる解説ですね!!
ンセとギター作品…濱田滋郎
マヌエル・マリア・) ポンセ (1882-1948)は、しばしば(メキシコ近代音楽の父と讃えられ、事実、没後30年を過ぎたこんにちも生国では高い敬愛を受けている。ポンセの名を広く知らせているのは抒情小曲(エストレリータ)の愛すべきメロディであるが、作曲家・指揮者・ピアニスト・教授として幅広く活動した彼は、一般に思われているよりはずっと器の大きな、そして近代的美意識に目ざめた音楽家であった。その筆になる交響詩、協奏曲、室内楽などの真価が世に認められるのは、 遅まきながらこれからであろう。
1882年12月8日メキシコ中部サカテカス州の町フレスニージョに生まれたポンセは、教養ゆたかな音楽好きの母親を持ち、早くからピアノに親しんだ。8歳でくハシカの行進曲>なる処女作ピアノ曲(この病気から治った記念の作だという)を書き、のちに18歳でメキシコ国立音楽院へ入ったときは、もはや何も習うことがなかったと伝えられる。1904年ヨーロッパに赴いて2年間滞在、大きな刺激を受け、故国メキシコの音楽水準を高めたいと望むようになった。作曲活動を進めるとともに1908年か国立音楽院の教授となって後進を導き、一時(1915-17) キューバでも活躍したことがある、その後、ふたたび思い立ってヨーロッパへ遊学、1925年から1933年までパリに住み、大家ポール・デュカス (1865-1
935)の知遇を得て多くのものを学び取った。帰国から最晩年(彼 1は1948年4月24日に没した)にかけてポンセがメキシコ楽壇に果した役割は以前よりさらに大きく。この国の音楽史上にけっして忘れることができない。
ポンセを語るさいに重要なことの一つは、1924年メキシコで識り合い、つづくパリ遊学期を通じて親交を深めたアンドレス・セゴビアのため、1篇のギター協奏曲《南の協奏曲》、数篇のギター・ソナタをはじめとする幾多のオリジナル作品を、この楽器に贈ったことである。 こうしてポンセは、ヴィラーロボス(ブラジル)、カステルヌオーヴォーテデスコ (イタリア~USA)、モレーノ ・トローバ、ロドリーゴ(スペイン)らと並び、“20世紀におけるギター音楽のルネッサンス”のために、最もいちじるしい貢献をはたす作曲家となった。
当代の名手ジョン・ウィリアムス (1941年メルボルン生まれ)がここにポンセの作品のみを改めて取上げたこと。とりわけ大作《スペインのフォリアによる変奏曲とフーガ》に理想的な名演を与えたことは、この作曲家の真価を、その一端なりと広く認識させる快挙であろう。 なお録音は1978年4月、ロンドンのAIRレコーディング・スタジオで、プロデューサー Roy Emerson、エンジニア Michael Stavrou のもとに行なわれた。
“スペインのフォリア”による変奏曲とフーガ
1930年頃、アンドレス・セゴビアのために作曲されたこの曲は、演奏時間の点からも、また内容の高度さという点からも、《南の協奏曲》や数篇のソナタに優るも劣らない、ポンセの代表的ギター曲と呼べるであろう。
変奏曲の主題として選ばれたのは、非常に古く、少なくとも16世紀まで起源をさかのぼることができるスペイン ― 真の発祥地はポルトガルだともいう ― の舞曲 <フォリアンの旋律である。特定の低音進行(あるいは特定の和声進行)をともなうこの旋律は、バロック時代の初期頃から器楽による変奏曲の主題としてさかんに利用された。最も有名な1曲にコレッリのヴァイオリン曲 〈フォリア〉があるが、ほかにもたとえばマラン・マレ、 C.P.E バッハ、ダングルベールなどすぐれた作曲家たちが〈フォリア〉による変奏曲の逸品を書き残している。ギターの世界においても、17世紀のスペインに重きをなした5複弦ギター(いわゆるバロック・ギター)の大家ガスパール・サンスや、19世紀の初めに6単弦ギター(こにんにちのギターにそのまま通じるもの)の地歩を確立した名演奏家兼作曲家フェルナンド・ソルが、ともに美しい〈フォリアとその変奏〉を後世に残した。
バロック時代の音楽に充分な興味と知識を持ち、セゴピアとの“共謀”によりヴァイスやA・スカルラッティの名前をかりて自作の“バロック画作品”を発表さえしたポンセが、〈フォリア〉の変奏を作曲する気になったことは不思議でない。ただし、この曲の場合、ポンセはバロック風のパスティッシュ(模造画)を仕上げようとはせず、近代楽派に立つ者としての自分自身を、細心に描き出そうと試みている。言いかえれば、非常な“器用さ”を持ち合わせていたために本性を見きわめられにくい作曲家であるポンセが、生真面目になって、己の内奥にあるものを、ありったけの技倆をふるって6弦上に造型してみた作品だと言える。
主題(レント、3/4拍子)
伝統的なフォリアの主題 (二短調)は明白に出されるが、クロマティック(半音階風)な和声づけが、すでに充分、近代的な陰影を添えている。
第1変奏(ポコ・ヴィヴォ、4/8拍子)
早くも拍子を2拍子系に変え、軽妙なアクセントで飾っていく。後半は3連音のアルペッジォがつづく。終りの和音は上声の導音をわざと解決せずに残している。
第2変奏(アレグレット・モッソ、6/4拍子)
ラント舞曲を想わせてなだらかに流れる。中頃、5小節にわたって出る変則アクセントが効果的。
第3変奏(レント、4/4拍子)
高・中声、低音の対話で始まる悲歌風の変奏。
第4変奏(ウン・ポコ・アジタート、3/8拍子)
高・中声が一貫して8分音符の歩みを進め、低声が16分音符一つずつ遅れながらそれについていく。緊張感をはらんだ変奏。
第5変奏(アンダンティーノ、2/4拍子)
ふたたび柔かな、打情味にみちた歌がきかれる。
第6変奏(アレグレット・エスプレッシーヴォ、9/8拍子)
ここで、これまでのニ短調からイ長調に転じる。 ただし、曲調は急に明るくなると言うのでもなく、クロマティックで近代的ニュアンスにみちている。
第7変奏(アンダンテ、3/4拍子)
ふたたびニ短調。 曲調はモダンだが、装飾音を軽く配し、オツな風情を感じさせる。3拍子の足どりからも“フォリア風”な変奏。
第8変奏(モデラート、3/4拍子)
やはりニ短調、 おもに3連音符のアルペッジォで作られている。和声的にはここで、古典的な平明さを取戻す。
第9変奏(アンダンティーノ・アフェットゥオーソ)
初めてニ長調をとる変奏。“情愛をこめて”の指定どおり、甘美な気配をおびている。
第10変奏(プレスティシモ、3/8拍子)
ニ短調で、 疾走する影のように急速な8分音符の列がすぎる。後半にいっとき現われるラスゲアード(かき鳴らし)がいちじるしい効果をかもし出す。
第11変奏(アンダンティーノ、6/8拍子)
転じて、 ハ長調の優美なシチリアーノとなる。複雑な変化和音や転調が用意されて、曲想は単純ではない。
第12変奏 (アニマート、3/4拍子)
“リトミコ(リズミカルに)”を指示があるように、軽快な舞曲調 ― スペインのファンダンゴのそれ ― をとる。ラスゲアードも加わって活気を強める。調性はニ短調に戻っている。
第13変奏(ソステヌート、6/4拍子)
厳格な2声のカノンで、独特の趣をかもし出す。
第14変奏(アレグロ・ノン・トロッポ、6/8拍子)
8分音符をそろえた小刻みな足どりを持っているが、2 回にわたり軽妙なリズムの遊びがまれる。
第15変奏(アレグロ・モデラート・エネルジコ、4/4拍子)
調性記号が外されイ短調のようにも見えるが、 じつは古代旋法的な傾きが濃い。しかも力強く決然をした、印象的な変奏。
第16変奏(モデラート、6/8拍子)
ニ短調(ないしニのエオリア旋法)による美しいトレモロ。このあたり。 性格のはっきりした変奏を並べて“山場を作っている。
第17変奏(アレグロ・マ・ノン・トロッポ、2/4拍子)
愁のうちに皮肉と笑いをこめた、カプリシューズな変奏。
第18奏(アングロ・スケルツァンド、2/4拍子)
用いられた音型こそ違うが、趣は前の変奏から受けつがれている。
第19変奏(ヴィヴォ・エ・マルカート、4/4拍子)
付点音符のにリズムに終始し、たいへん情熱的な使奏。
第20変奏(アンダンテ、4/4拍子)
桜めやかなハーモニックス音をちりばめた最終楽章がつぎに来るフーがを絶妙に用意する。
フーガ(モデラート、3/4拍子、ニ調)は、20に及んだ変奏曲をしっかり締めくくるだけの重厚さと、情緒の濃さを与えられている。主題はフォリアのそれと(少なくとも気分的に)関連をそなえ、終曲に置かれた、格別の規模を持つ変奏と見なすことも可能であろう。
追記しておくと、この曲の譜面はドイツおよびイギリスの Schott 社から1932年にセゴビアの校訂で出版され、今日では音楽之友社から日本版も出ている(セゴビア/クラシック・アルバム13)。
●前奏曲(Preludio)
●バレット (Balletto)
これら二つの小品は、ともに当初“S・L・ヴァイス”の名で発表されたが、のちにポンセの筆になるものと判明した。前者はホ長調6/8拍子、後者は嬰ハ短調4/4拍子により、擬古趣味ながらきわめて流麗な、小気味よい2曲である。
●3つのメキシコ民謡
a) 小島うりの娘 (La Pajarera)
b) わが心よ、君ゆえに (Por ti mi corazón)
c) ラ・ヴァレンティーナ (La Valentina)
ポンセはメキシコの民謡を蒐集することにも力を注ぎ、 しばしばそれらに適切な和声や対旋律を添えて、好個のピアノ小曲とした。これら3曲は、ポンセ自身がその中のとくに美しいメロディーを選びギター用に編み直したもので、やはりセゴビアの連指を付し1928年に Schott から刊行された。このうち〈ラ・ヴァレンティーナ〉は、 メキシコ革命の折、兵士たちが口ずさんだ唄として名高
●ワルツ (La Valse)
小品ながらポンセらしい味がある。ニ長調だが音階上の第4音を半音高めリディア旋法への傾きを持たせているため、微妙に無重力的な立体感が生じている。
1937年 Schott より出版。
●しおれた心 (Marchita el alma)
●8ヵ月前(Hace ocho meses)
●愛する母 (Yo adoro a mi madre)
これらの3曲もポンセが自国の美しく人好きのする民謡から編作したもの。ただし、これらの場合、編曲者はポンセ自身でもセゴビアでもなく、近年夭折したイギリスのギタリスト、ローランド・ハーカー (Roland Harker)である。ハーカーはセゴビアの門下生で、ウィリアムスとも交友を持っていた。

YouTube のジョン・ウィリアムズ – トピックにこの曲もありますよ!!
動画の時間は24分ちょいと長いんですが、聴き応えありますよ!!
時間のある時に、最初から最後までぶっ通しで聴くことをオススメします!!
2025年9月7日追記
上の方に「ギターの響きしか録音していません」と記載したんですが、以下のサイトでこのレコードに関するジョン様の発言を見つけました
Cedar vs. Spruce Top Guitars According to John Williams | Classical Guitar
フレータ・ギターの「魂」が込められていると感じた最後のレコードは、ポンセのレコードです。このレコードは、非常に近い距離で録音しました。まるで部屋の中にいるかのように録音し、実際に録音後に部屋の真ん中に座って演奏し、同じ音量でレコードをかけましたが、私の耳にはほとんど違いがありませんでした。まるで自分がそこに座っているかのように、部屋の延長ではなく、まさにそこに座っているかのように、できるだけ近い音にしたかったのです。そうしないと、ギターがあなたに向かって演奏しているのではなく、あなたに向かって演奏しているような、別の種類のプレゼンテーションで録音または演奏すると、少し硬く聞こえてしまいます。これがパーカッシブな部分で、私の場合は硬い爪のせいで、それが誇張されているのです。しかし、実用上は十分に使える、とても良い爪でした!
翻訳 by Google さん
The last record that I feel had the “soul” of the Fleta guitar was the one of Ponce, where I recorded it very, very close. I recorded it as if I was in the room, and in fact I afterwards sat and played in the middle of the room, put the record on at the same volume, and the difference to my ears was hardly anything. I wanted it as close as if I was sitting there, not an extension of the room but sitting right there. And unless you did that, if you recorded or played in another kind of presentation where it was playing at you as opposed to with you, it sounded a bit hard. And that’s this percussive thing, which in my case is exaggerated because of hard nails. But serviceable, very good nails for practical reasons!
フレタの音をその場で聴いているように録音したんだそうです
僕の感覚、あながち間違ってなかったみたいで嬉しいです!!

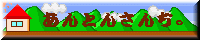
コメントを残す